1998年4月に修士論文計画の発表会を行なってから後、しばしば過労の諸症状に倒れ、本来なら同年12月に迎えるはずの修士論文発表会が1年遅れて1999年になりました。以下はその12月22日の発表会に先んじて八王子大学セミナー・ハウスにこもって作成し、12月13日に提出したレジュメです。1月27日に提出する論文最終稿の雛形ということで、発表会以後本論がかなり変わる可能性がありますが、とりあえずここまでの到達点ということで。
1999.12.18記
−独自性と有効性の検証を通して−
学生番号 8971005 氏 名 川村 龍俊
主査 幸田一男教授 副査 根来龍之教授
目 次
1 はじめに
2 研究の目的
3 研究の構成
4 小野桂之介による先行研究の評価
4.1 ミッション経営の前提とミッションの定義
4.2 ミッション経営の研究の実際
4.3 小野式ミッション経営
5 ミッション経営の定義
5.1 ミッションの再定義
5.2 ミッション経営の定義:三面等価の原則
6 ミッション経営の実例検証
7 ミッション経営の隣接分野との比較
7.1 経営理念に基づく経営との比較
7.2 ドメイン論に基づく経営との比較
7.3 企業倫理論に基づく経営との比較
7.4 ミッション経営の独自性
8 ミッション経営の有効性の検証
8.1 適用するための方法
8.2 ミッション経営を適用した企業の例:明工グループ
8.3 ミッション経営の有効性
【主な参考文献】
1997年の暮れに慶應義塾大学教授小野桂之介が上梓した「ミッション経営の時代」という本では、その副題に「社会的使命が企業を高める」とあるように、企業の社会的使命=ミッションを企業経営の旗頭に掲げることを奨励している。小野が「ミッション経営」という言葉にたどりついた背景には「誰もが、売上げや視聴率といった目の前の直接的な結果と自分の都合だけを見つめながら行動しているのではないか」という疑問があった。この疑問に対する答えを出すべく小野が取り組んだのは、少しでもいい世の中にするよう発信するということであった。その手始めとして「広い時空間意識を持ち、独自の信念と使命感に従って企業をリードしている経営者の話を聞き、そこから抽出したエッセンスをもとに」世へ問いかけてみようとしたのである。株式会社カンキョー藤村靖之社長・株式会社林原林原健社長・株式会社堀場製作所堀場雅夫会長・オリックス株式会社宮内義彦社長・KOA株式会社向山孝一社長・株式会社ミツトヨ沼田惠副会長・ラッシュすみだ津幡英夫会長という七人の経営者に自らインタビューを試み、その会話の中から拾い出した経営のあり方をまとめたものがこの時点でのミッション経営の内容である。
1)小野桂之介以外の視点から「ミッション経営」を検証する。
2)「ミッション」経営の隣接分野との比較を行ない、独自性を評価する。
3)「ミッション経営」を定義する。
4)「ミッション経営」の実務への適用を検討する。
研究の目的を達成するために、次の手順で研究を行なった。
1)小野桂之介の提唱するミッション経営の類型化を行なった。
2)小野の視点以外からのミッション経営の定義仮説の打ち立てを行なった。
3)小野がインタビューした経営者・それ以外の経営者の言葉から仮説を検証した。
4)経営学の他の分野とミッション経営を比較し、独自性を明らかにした。
5)ミッション経営を実際の経営に適用した例を検証し、有効性を実証した。
6)これから明らかにされるべきミッション経営の問題点を抽出した。
4.1 ミッション経営の前提とミッションの定義
小野は、日本の企業社会が3つの重要な変革を迫られていると説く。その第一は「企業倫理の再構築」、第二は「企業活力の回復」、第三は「株主主権の強化」である。三つの変革課題はそれぞれ企業活動の別々の側面に現れてはいるが、その源をたどると、実はどれも根っこは一つ、「どのような使命感をもって企業活動に当たるのか」という原点に行き着く。ここを明確にし、経営者自らはもちろん、従業員全体にそれを徹底すれば、問題は自然に解消に向かうのみならず、企業自体も一層発展しやすくなるように思われる。一方、ミッションとはなんであるか。小野は「社会的使命」の代わりに「ミッション」という表現を用いると明言している。
4.2 ミッション経営の研究の実際
小野が選んだ七人の経営者の、企業経営に取り組む基本的な考え方と、体験談の内容には、これから始まる新しい世紀に向かって企業経営者が持つべき使命感を考える上で参考になる普遍的な要素が含まれている。まずその一つは、「経営者が決めなければならないミッションには二つの異なった種類がある」ということである(図1参照)。
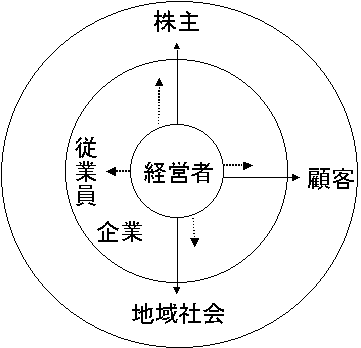
図1 経営者のダブル・ミッションと企業ミッションの四要素(c小野桂之介 1997)
その第一は「企業が社会に対して果たすべき使命」である。企業がどのようなミッションを担うことにするかは、企業活動の責任者たる経営者が、従業員や、株主の意見を聞きつつ決めなければならない(図1、実線矢印)。
第二は、「その経営者自身が、指揮する企業の長期にわたる発展過程の中で、(当該企業に対して)どのような役割を果たすべきか」というものである(図1、破線矢印)。企業の経営者には、リードする組織の長い歴史の中で、自分が担当する一区切りの期間に何を中心的な仕事として成し遂げるべきかを考え、それを明確な目標として四六時中考え続けることが求められる。
次に、ミッションというものの中身は、「誰」のために「何」を実現しようとするのかによって定まる。七人のトップ経営者が企業のミッションについて語る中で登場する「誰」には、大きく分けて四つの社会構成メンバーが含まれる。その四つとは、企業が貢献しようとする社会の主要な構成メンバー、すなわち、顧客、株主、従業員、地域社会である(図1参照)。ただし、従業員は、「経営者個人」という立場から見れば、企業という組織的仕組みとともに貢献対象としての社会に含まれうる。しかし、「企業」という立場からその果たすべきミッションを考える場合は、経営者とともに、行動主体の側(図1、企業を表す内側の円)に立つことになる。
経営者が決定する「企業のミッション」の照準は、顧客・株主・地域社会という三種類の社会構成メンバーに向けられる。さらに、経営者が決定するもう一つの使命である「経営者のミッション」については、その対象として、経済活動の仕組みとしての企業、および、その行動主体である従業員が含まれてくる。4.1に述べた第一の「企業倫理の再構築」という変革課題は、(広義の)顧客と地域社会に向けたミッションの明確化を求めている。第二の「企業活力の回復」という課題については、主として顧客に向けたミッション意識の再確認によってさまざまな突破口が見出されよう。そして第三の「株主主権の強化」という課題に対しては、上記の四種類の社会構成メンバーに対する自らの価値観に基づく優先順位を明確化し、それに基づいてこの外圧に対する経営者としての旗幟を明らかにする必要がある。また、経営者自身というもう一人のステークホールダーも存在するはずである。
4.3 小野式ミッション経営
前提条件:ミッションとは社会的使命のことである。今の日本企業(社会)には社会的使命感が不足しているので「企業倫理問題」「企業活力問題」「株主主権問題」が起きている。これからの企業経営には社会的使命(感)が必要である。そうでないと社会(企業)がよくならない。
研究方法:社会的使命(感)を持っていると思われる企業トップにインタビュー。その内容を分析して、共通に持っている認識を抽出。共通項を分類して特徴ごとに分類。
研究成果:経営者が担うダブル・ミッションの発見(企業が社会に対して果たすべき使命と、経営者がその企業・従業員に対して果たすべき使命)。四つのステークホルダー(顧客・株主・地域社会・従業員)の限定。(総論として)経営者のステークホルダー(の欲求)との闘い。
5.1 ミッションの再定義
小野は、自らのもつ社会や日本企業への不満・不安から、その根拠を社会的使命(感)の欠如ととらえ、ミッション経営を提唱した。それは、小野によって社会的使命(感)=ミッションを持つとみなされたトップ経営者へのインタビューから導き出されただけのもので、これには極端な恣意性が残る。ミッション経営が経営の目的なのかそれとも方法論なのか、あるいは別のなにものなのかを見つめなおし、小野の持つ不安を共有しつつも、より普遍的な概念として捉え直すことはできないものだろうか。
まず、ミッションについて考えてみる。もともとはキリスト教の使節団やその使命を表すことばだったが、昨今では「企業が一番最初に掲げる企業存在目的もしくは目標」のように使用されてもいる。その場合、ミッションは、「探して見つけるもの」でもありうるし、「作り出すもの」でもありうる。しかし、わざわざミッションというとき、そこにはもっと切実な、逆らい難い、強いものが込められていると考えてはどうだろうか。
元の語義にかえって考えてみるならば、ミッションとは「神の命令」である。人はそれに背くことを「許されない」。日本においてはこのような強力な「命令」は、第二次世界大戦が終結するまでは「天皇の名のもとに」発令されていた過去があるが、戦後の米国による民主主義政策のために神はいなくなってしまった。
現在の企業において、上記したような強力な命令=根拠をもって経営がなされているだろうか。一つあるとすれば、利潤追求がそれにあたるだろう。利益主義・拝金主義による戦後の復興は1990年代初頭まで右上がりの成長を見せ、バブル経済の崩壊からは零落の一途をたどり、平成不況と呼ばれる混迷の時代を迎えている。振返ってみると、日本は二回、神を失ったことになる。天皇と金だ。天皇はさすがにもう帰ってこないと思われるが、拝金主義は根強く残っている。しかし市場においては金が万能の神ではないことを消費者が知り始めた。海外で急速に広まり出し、日本でも経団連を中心にその運動が広まりを見せているコーポレート・ガバナンスがその良い例だろう。金のためにの自分勝手はもう許さない、という風潮と解してもよいし、建前であろうと資源の浪費や環境破壊への歯止めについての世評が一般化したからと言ってもよい。いずれにしろ、企業側が金を神だと思いたくとも、市場がそれを許さなくなってきているのだ。
では、本当にもう神はいないのだろうか。いや、企業にとっての神はいる。それも、二人もいる。
一人は、ステークホルダーという神である。この神は、企業をとりまく環境そのものであるが、顧客になったり、株主になったりと変幻自在である。もう一人は、企業というよりもその企業のトップにだけ顕現する神であり、夢やひらめきといった明るい顔でお告げをすることもあれば、宿命という、まさに天皇の勅命のような形で一方的に命令だけしていくこともある(図2参照)。
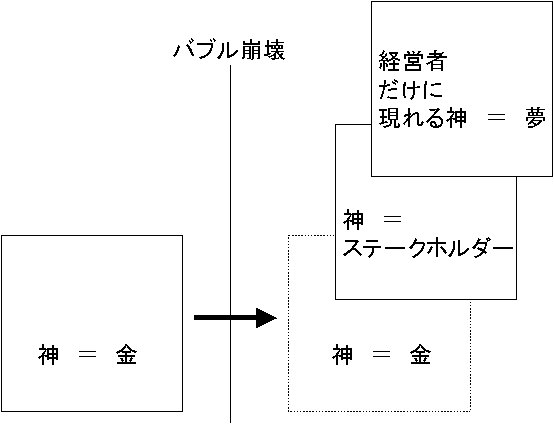
図2 ミッションを授ける神の時代的変遷
こうして、ミッションをくだす神が現在の日本の企業にもきちんと「いる」ことがわかったので、これによって、企業経営の目的が、今や「利潤追求」だけではなく、むしろそれは存続のための当然の前提として、更に「社会貢献(ステークホルダーの欲求を満たす)」と「(経営者自身の)自己実現」が足されていることが明確になった。
以上の考察により、ミッション経営におけるミッションとは、小野の定義する「社会的使命(感)」というあやふやなものから「経営者個人における夢や宿命の達成」「ステークホルダーの欲求を満たす」「(利潤追求)」の三つの使命(ミッション)の三位一体であると再定義できる。
5.2 ミッション経営の定義:三面等価の原則
ミッションには三つの使命があるが、これらは単純に同等の意味を持つというよりも、階層をなしていると考えた方がわかりやすい。すなわち、土台としての「利潤追求」の上に本体である「ステークホルダー満足」が建っており、その住人が「夢」や「宿命」を抱えていると考えられるのである。この「家」を外から見たときには基本的には本体しか見えないが、ときどき住人が外へ顔を出すというイメージであろうか。住人なしの家はあり得ない(図3参照)。
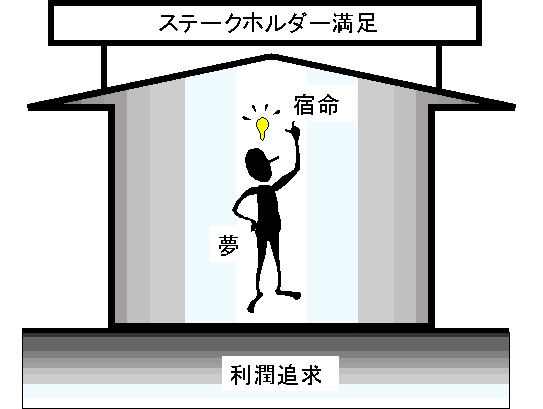
図3 ミッションの三位一体
つまり、この三つのうちの一つのミッションを抱えているからといって、その企業や経営者がミッション経営を行なっていると考えるのは早計なのである。むしろ、「三位一体ミッション」を持っているかどうかこそが重要なのだ。また、ミッションを持っていればその企業がミッション経営を行なっていると考えるのもまだ早い。小野が行なったように、具体的に経営している企業が「社会的使命(感)」を持っていると考えられるので、何らかの経営状態そのものがミッション経営と「呼ばれる」のである。
ミッション経営はまだ新しい概念であり、学問的領域において理論構築されたわけではなく、実際の企業経営のあり方に名付けたものである。ある企業を見て「ミッション経営をしているか」どうかの判定は可能かもしれないが、ある経営者や従業員がミッションを抱えているからといって「ミッション経営をしている」と断ずることはできない。
ミッション経営とは理論というより状態であるが、その状態が確認できるためには経営者がミッション(三位一体ミッション)を持っていることが大原則である。次に、三位一体ミッションのうち最も目につくところの「ステークホルダー満足」がステークホルダーによって「満足されている」ことが必要であろう。ステークホルダーは小野説に従うなら(図1参照)、主に株主・顧客・地域社会・従業員(経営者含む)の四つに分けられるが、実際には更に多くのステークホルダーが存在することは当然考えられるべきであろう。
そして、何よりも重要なのが、なぜミッション経営が望まれるか、という問題である。ここで本研究では、「ミッション経営はよい経営」であるという前提を持っていることを明らかにしたい。なぜなら、ミッション経営が取りたてて問題として検証するに値しないと考えたなら、取り上げるわけがないからである。むしろ、小野の問題提起には積極的に関与したい。小野は、未来の日本(企業)のあるべき姿がミッション経営によって見えてくると考えているが、それは、現在に欠けている部分(社会的使命)を埋めることができるからである。つまり、欠けたピースを埋めて、完全版を作ろうという考え方なのである。
ミッション経営が理念ではなくて状態であることにもう一度視点を戻すと、未来に向けて何をしようとしているか、ということが当然評価対象になるけれども、もっと短絡的に重要な現象がある。それは、「事業の成功」である。ミッション経営は企業によって営まれている現象であり、企業経営の状態なのだから、当然その企業は成功していなければならない。この成功は、三位一体のミッションに照らしてそれを満たしていると同時に、観察者やステークホルダーによっても納得されていなければならない。
ここで、ミッション経営の三面等価の原則を提唱する(図4参照)。
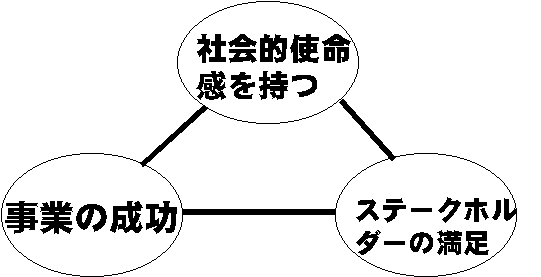
図4 ミッション経営の三面等価の原則(c根来龍之 1999)
この図は、各円の要素がそれぞれが相互に連関しあいながら、全体としてミッション経営を形作っていることを表している。三位一体ミッションの定義の各要素(図3参照)とこの図の要素が一対一対応しているわけではないので注意が必要である。各要素それぞれについては、主格である経営者(あるいは企業)と、客体としての観察者(場合によってはステークホルダー)の相互が、その要素の示す内容について納得している場合に成立すると考える。
多少複雑になったが、ある企業がミッション経営を行なっているかどうかの基準として、この三面等価の原則が適用されているかどうかを考えればよい。その場合、まず各要素が満たされているかどうかを検証し、三つとも満足の行く結果になっていればよいのである。ただし、この検証に、科学的な合格基準を持ち込むのは難しい。というのも、企業によっておかれている環境も業務内容も企業規模も違うこと、経営者自身が「三位一体ミッション」という考え方を現時点では誰も持っていないこと、観察者が考える成功基準・ステークホルダー基準・経営者のミッションと企業側のそれらが一致するとは限らないこと、などが予想されるからである。
しかし、現状の企業自体も激しく変化しているのであり、ミッション経営が理論というよりは状態を表す概念である以上、こうした問題は個別に対応していくしかない。こうしたことを了解した上で、実際に検証にあたるときには、まず、その企業トップの言葉に耳を傾け、そこにミッションを認められたら、続いて他の二つへと検証を進めていくのがよいだろう。
この章では、ミッション経営の三面等価の原則を用いて、実際の企業の検証を行なう。まず、小野が実際にインタビューを行なった三企業(堀場製作所・林原・ラッシュすみだ)を取り上げ、次に小野の言及していない三企業(mkタクシー・ヤマト運輸・京セラ)についても同様の検証を試みる。この三企業を取り上げた理由は、経営者がミッションに関わる発言を行なっている可能性があると思われることが第一、利潤追求の結果まともな利益を出していることが第二である。以下に例として堀場製作所の分析結果を示す(表1)。結果として、六企業それぞれのミッション経営が浮き彫りにされた。
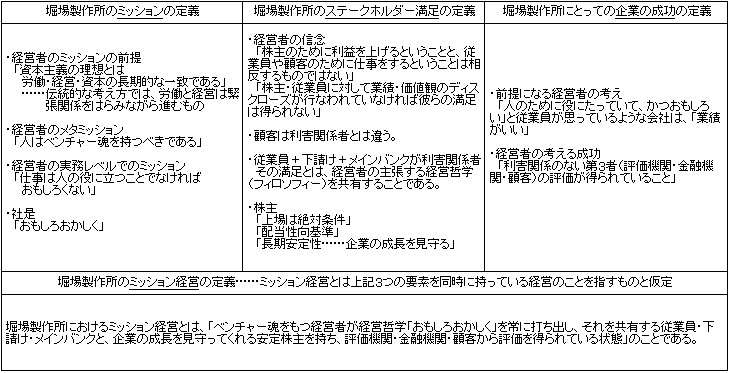
7 ミッション経営の隣接分野との比較
7.1 経営理念に基づく経営との比較
ビジョナリーカンパニーを例にとって比較を試みる。
コリンズとポラスによる「ビジョナリー・カンパニー」に習えば、五十年以上にわたって活躍し続けることができた企業に共通する一つの特徴は、理念と戦略・経営システムの一貫性であった。具体的には、社員に対する経営管理教育の実施、経営者と各階層の社員とのコミュニケーションの場の設置、社内報等を通じたきめ細かい情報開示・情報提供の実行、の三つを推進することが重要である。
経営理念に基づく経営には、「ステークホルダー満足」と「事業の成功」はあるが、肝心の「ミッション」が存在しない。
7.2 ドメイン論に基づく経営との比較
アーサーアンダーセンの提唱するミッション・ステートメントに基づく提案との比較を試みる。
世の中は、これまでに経験したことのないスピードで激変中である。この変化に対応するためには新しい価値観を創造することが必要になる。この新しい価値観の構築に必要なのはミッション(Mission)である。日本の殆どの企業では、昨年比何パーセントという「数値目標から入る経営管理」が習慣的に取り入れらているが、欧米の殆どの企業においてミッションが設定されている。企業におけるミッションとは「経営の意思」として企業の存在意義、事業、願望、価値観、などを表したものである。このミッションを経営の最上に掲げ、戦略、目標、重点方針へと展開・実行していく戦略推進手法をミッションマネージメントという。環境の変化が激しく、企業価値の根本的な見直しが必要とされる今日こそ、ミッションの再構築とそこから始まる経営管理の実践が求められている。
ドメイン論に基づく経営においては、ミッションという言葉は使われていても、その意味は「三位一体ミッション」とは遠く、企業目的達成のための必需品というイメージがぬぐえない。
7.3 企業倫理論に基づく経営との比較
ここでは、企業倫理論に基づく経営との比較を試みる。
企業倫理誕生の背景には、企業不祥事の続発、情報・通信技術の進展、グローバル化と市場経済への移行、市民意識の向上とマスメディアの発達、環境問題への関心の高まり、そして企業の社会的責任の増大といったことがらが指摘できよう。日本においては、他の企業環境をとりまく諸問題と同様、近年になってから欧米の企業の方向づけにならう形で企業倫理の問題が取りざたされるようになってきたが、歴史的にみれば、戦後のコーポレート・ガバナンスを担った銀行が、市場経済の成熟に伴い、第一にして巨大なステークホルダーの位置を降りたことにより、企業の経営陣が右上がりの経済状態にあぐらをかいて現状維持に努める姿勢に転化していったことが大きな特徴であろう。企業倫理とは企業理念のシステム化のことであり、それはトップの生き方のことであると言える。
企業倫理論に基づく経営とは、ミッションやステークホルダー満足については関連してくるものの、事業の成功という点については重要視されていない。ミッションについても、小野式ミッション=社会的使命(感)に近いものであって、三位一体ミッションには程遠い。
7.4 ミッション経営の独自性
上記のようにミッション経営の隣接分野との比較を試みたが、ミッション経営という概念は独自性を強くもっていることが明確になった。なお、小野説によるミッション経営は、社会貢献を強く訴えているわけだが、すでにミッション経営という概念はその部分だけでは成立しないので、繰り返しての言及は避ける。
8.1 適用するための方法
ミッション経営とは方法論ではなく状態を示す概念であるということは繰り返し述べてきたが、それだけでは企業の判定基準にしかならない。小野の理想は日本の企業経営者にミッション経営を行なってもらうことであり、その実現のためには実務への適用が不可欠なのである。
方法論ではないながらも、ミッション経営概念を把握し理解した上で経営者が経営することは不可能ではあるまい。つまりは、自らの経営状態を数字で把握する以外のガイドラインとして、常に三面等価の原則を思い浮かべ、指揮の結果を反芻することであろう。
六社の検証(6章)からも明らかなように、一口にミッション経営を行なっているといってもその内容は企業によって極端に違う。その違いは企業トップのミッションの違いにあると言えよう。三位一体ミッションの中には、経営者本人にしか現れない夢や宿命が含まれている以上、それは当然であると言える。個別の企業が個別の経営を行なっていても、大きな意味でミッション経営であると言い得ることから、事業への適用に際しては手本や見本は存在しないことを前提として取り組む必要があるだろう。
まず、第一に、経営者が三位一体ミッションの中の「経営者個人の夢や宿命」を持っていなくてはならない。これは、努力して探すことは無駄ではないが、作りあげられるという類の作業ではない。これを行なうことが自己実現であり、行なわないときには事業を撤退するくらいの強力なものでなくてはならない。代替のきく夢や、時と共に薄れるひらめきや、思い込みにすぎない宿命などではミッションたり得ない。
次に、「ステークホルダー満足」をかなえなければならない。その経営者にとってのステークホルダーは、小野のいう四者だけで足りるのか。自社にとって他にもっと気にしなければならないステークホルダーがいるのではないか。彼らにとっての満足とは何か。むしろ、彼らからの声こそがミッションなのであるから、はじめからステークホルダーがあいまいなままでははじまらない。
そして、利潤追求のための組織や資産や生産物や方法論を持っていなければならない。多くの場合、ここに関しては、どの企業も必死になっているから、特に心配はいらないが、これまでに行なってきたことがこれからも通用するとは限らないから、よくよく注意する必要がある。
ここまでを経営者がまず納得できて、はじめて実際の適用プロセスを考えることができる。
経営者はミッションを持ったが、その企業にとってのステークホルダー満足をどのように叶えていくべきであり、また、どのような評価をもらうことで事業の成功を確信するのかを企業サイドから明確にしなくてはならない。そして、各ステークホルダーからの意見を聞くためのルートを確保しておかなければならない。
こうして考えてみると、よくよく多くのことをミッション経営は企業や経営者に要求していることがわかる。しかし、おおもとは経営者自身のミッションなのだから、後戻りはできない。
8.2 ミッション経営を適用した企業の例:明工グループ
明工グループとは、独立した5つの企業の総称である。営業内容から見ると、配線器具の製造販売を行なっている4社(明工商事・明工社・明工電器・福島明工社)と、配電盤の受注生産・販売を行なっている明工産業1社の2つのグループに分けることができる。
創業者1986年の創業者の死後、その長男がグループ各社の指揮をとってきたが、大きな目標は売上高と企業イメージの向上だけで、企業経営を通じての夢を語ることはなかった。1999年にその長男が将来の後継者候補という前提でミッション経営という概念を持ち込み、全社員個別面接を行ない、現社長にグループ統合のち上場という具体的な目標を宣言させ、営業や取締役とは泊まり込みで話し合いをもち、半年後には配線器具グループ4社ではあたかも1社のごとく機能するような新組識への変更を、明工産業では思い切った若返り人事を行なった。全社員の顔と名前が一致しているからこその英断であったが、何よりも当人が後継者としての当事者意識を、ミッションという概念によって強く保持していることが大きい。社内の雰囲気は完全に明るくなった。
8.3 ミッション経営の有効性
明工グループを例にあげてミッション経営の有効性を検証してみたが、この企業グループの場合はかなり固有の条件が含まれていることを指摘する必要があるだろう。まず、キーとなる経営者が、現社長ではなく後継者であること、後継者である立場を利用して現経営者にミッション経営を伝えて現経営者をその気にさせたこと、危機管理の方策としてミッション経営の適用に踏み切ったこと、もともと他の経営に関する方法論がほとんど普及していなかったこと、ミッション経営を論じられるブレーンを社外から呼び込み、社員として雇用したことなど、特殊な面が多々数え上げられる。 また、この時点では、ミッション経営ということばはおろか、ミッションということばも社内的に普及させていないことも重要である。もしここでそのような、概念そのものの普及をはかろうとしたら、アンダーセン流ミッション・マネジメントと同じような、方法論としてしか広まらないからである。しかし、まだこの実験は半年を経たばかりであり、有効性をここで断ずるのは早計であると言わざるを得ない。
しかし、ミッション経営は方法論ではなく状態を指す、ということは大変重要である。言い換えると、方法は、ミッションを叶えるためならなにを使ってもかまわないということである。そして、ミッション経営かどうかということそのものは、経営者だけがしっかり把握していればよい。法人格とは、すなわちトップの人格なのである。
[1[小野桂之介著:"ミッション経営の時代",東洋経済新報社,(1997)
[2]アーサーアンダーセン編:"ミッションマネジメント",生産性出版,(1997)
[3]一條和夫著:"バリュー経営",東洋経済新報社,(1998)
[4]マコワー著,下村満子監訳:"社会貢献型経営ノすすめ",アイデイ,(1997)
[5]高橋俊介著:"知的資本のマネジメント",ダイヤモンド社,(1998)
続けて1999.12.22に行なわれた発表のスライドショー。コテンパンの評価をいただいたことで、1999年度の修了は見合わせることに決定。本来はお目にかけることそのものがはばかられる内容なんですが、記録ということで。
1999.12.23記